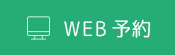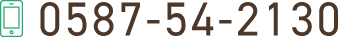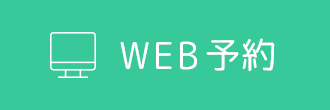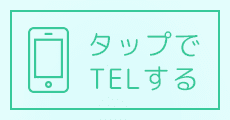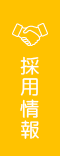親の歯並びは子どもに遺伝する?
 皆さん、こんにちは。江南市布袋のつかもと歯科です。
皆さん、こんにちは。江南市布袋のつかもと歯科です。
「自分の歯並びが悪いから、子どもも同じようになるのでは?」と心配される親御さんは多いのではないでしょうか。確かに歯並びには遺伝の影響もありますが、すべてが遺伝で決まるわけではありません。今回は、歯並びが親からどこまで遺伝するのか、逆に生活習慣などでどのように変わるのかを詳しくお伝えします。
子どもの歯並びが遺伝で決まる範囲
はじめに、親からの遺伝によって決まりやすい子どもの歯並びの範囲、特徴を解説します。
骨格の特徴は遺伝しやすい
歯並びに大きく影響するのは、顎の骨格です。顎の大きさや形は遺伝の影響を強く受けます。例えば、顎が小さく歯が大きいと歯が並びきらず、ガタガタの歯並び(叢生)になる可能性が高まります。逆に顎が大きく歯が小さいと、歯と歯の間に隙間ができやすくなります。
歯の大きさや本数も遺伝する
歯の大きさや形も遺伝的要素が大きい部分です。親御さんの歯が大きい場合、子どもも同じように大きな歯が生えやすい傾向があります。また、まれに永久歯の本数が少ない「先天性欠如歯」も遺伝性があるとされています。こうした骨格的・形態的な特徴は、子どもの歯並びに影響を与えます。
骨格性の噛み合わせのズレ
出っ歯(上顎前突)や受け口(反対咬合)など、骨格的な噛み合わせのズレも遺伝しやすいです。親御さんが出っ歯の場合、同じように子どもも上顎が前に出やすい骨格を受け継ぐ可能性があります。ただし、必ずしも全く同じ状態になるとは限りません。
子どもの歯並びが影響を受ける遺伝以外の要素
次に、子どもの歯並びに影響を与える遺伝以外の要素を解説します。
指しゃぶり・舌癖などの癖
遺伝だけでなく、日々の生活習慣や癖も歯並びに大きく関わります。特に幼少期の指しゃぶり、舌で歯を押す癖、頬杖などは、歯の位置に力が加わり、歯並びが乱れる原因になります。長期間の指しゃぶりは出っ歯の原因となり、舌癖は前歯の傾きを引き起こすことがあります。
口呼吸
口で呼吸する癖も見逃せません。通常、舌は上顎に触れて顎の発育を内側から支えていますが、口呼吸が続くと舌が下がりやすく、上顎の発育が妨げられます。その結果、歯が並ぶスペースが不足し、歯並びがガタガタになることがあります。
食生活の影響
最近は、やわらかい食べ物が多く噛む回数が減っている子どもが増えています。噛む力が少ないと、顎の発達が十分に行われず、歯がきれいに並ぶスペースが確保できなくなります。よく噛んで食べる習慣を身につけることが、顎の正常な発育を助け、将来の歯並びにも良い影響を与えます。
虫歯による早期喪失
乳歯の虫歯が進行し、抜けてしまうと、永久歯が正しい位置に生える目印が失われます。その結果、歯がズレて生えてくることがあり、噛み合わせや歯並びに悪影響を与えます。乳歯だからと油断せず、しっかりケアをして虫歯を防ぐことも大切です。
早期の予防とチェックが大切
歯並びの乱れは、癖や生活習慣を見直すことで予防できることが多くあります。お子さんの指しゃぶりや口呼吸に気づいたら、早めに専門家へ相談しましょう。また、噛み合わせや顎の成長の様子は、定期的に歯科医院でチェックすることをおすすめします。
まとめ
 お子さんの歯並びは、親からの遺伝だけでなく、生活習慣や癖、虫歯の有無など、さまざまな要因で決まります。遺伝だからと諦める必要はありません。小さな頃からの習慣や予防が、きれいな歯並びを育む大きなポイントです。つかもと歯科では、子どもの歯並びや噛み合わせの相談を受け付けています。気になることがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。
お子さんの歯並びは、親からの遺伝だけでなく、生活習慣や癖、虫歯の有無など、さまざまな要因で決まります。遺伝だからと諦める必要はありません。小さな頃からの習慣や予防が、きれいな歯並びを育む大きなポイントです。つかもと歯科では、子どもの歯並びや噛み合わせの相談を受け付けています。気になることがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。