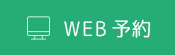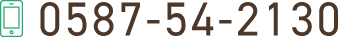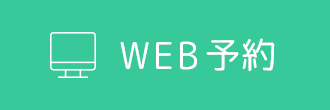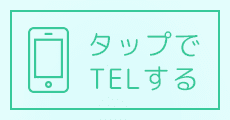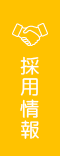歯周病の予防や改善に効果がある歯磨き粉について
 皆さん、こんにちは。江南市布袋のつかもと歯科です。
皆さん、こんにちは。江南市布袋のつかもと歯科です。
歯周病は成人の多くがかかっていると言われるお口の生活習慣病です。放置すると歯茎が腫れたり、出血したりするだけでなく、最悪の場合には歯を失うこともあります。そこで今回は、歯周病の予防や改善に効果がある歯磨き粉の選び方と、正しいブラッシング方法について詳しくお話しします。
歯周病に効果がある歯磨き粉の成分
歯磨き粉にはさまざまな種類がありますが、歯周病対策を考える場合は、成分に注目することが大切です。
抗菌成分
歯周病は、プラーク内に存在する歯周病原細菌(代表的なものとしてPorphyromonas gingivalisなど)が主な原因です。これらの細菌が歯と歯茎の隙間(歯周ポケット)に繁殖し、炎症を引き起こします。
このため、細菌の増殖を抑制できる抗菌成分を含む歯磨き粉の使用は、歯周病の進行予防に役立ちます。代表的な成分には「クロルヘキシジン」があり、世界的にも歯周病予防に有効とされています。ただし、日本では濃度によっては医師の処方が必要で、長期間の連用は味覚障害などの副作用が報告されています。市販品では「IPMP(イソプロピルメチルフェノール)」や「トリクロサン」が使用されている場合があり、歯周ポケット内の細菌数を減少させる効果が期待できます。ただし、使い方や頻度は歯科医師の指導のもとで行うことが大切です。
抗炎症成分
歯周病では歯茎の炎症が慢性化しやすく、出血や腫脹を繰り返します。炎症を抑える成分が配合された歯磨き粉を併用することで、歯茎の健康を保つ手助けになります。
「グリチルリチン酸ジカリウム」は、甘草由来の天然成分で、抗炎症作用と抗アレルギー作用が認められています。また、「トラネキサム酸」は止血作用と抗プラスミン作用により、歯肉の出血傾向を抑える働きがあり、歯周炎に伴う歯茎からの出血軽減が期待されます。ただし、根本的な治療は機械的なプラーク除去が基本であるため、歯磨き粉はあくまで補助的に活用しましょう。
歯垢(プラーク)を除去しやすくする成分
歯周病の最も大きなリスク因子は、歯面に付着するプラーク(細菌の集合体)です。プラークは時間とともに成熟し、歯石化すると歯ブラシでは除去できなくなります。
「ポリリン酸ナトリウム」などの歯垢分散成分は、プラークの形成を抑制し、除去しやすくする働きがあります。また、歯磨き粉に含まれる研磨剤(清掃剤)の粒子が粗いと歯面や歯茎を傷つけ、知覚過敏の原因になることがあります。研磨剤の粒径が微細で、歯面を傷つけにくいものを選ぶのが安心です。歯垢除去の主体はブラッシング技術であることを忘れず、成分はあくまでサポート役です。
歯周病予防に効果的なブラッシング方法
いくら良い歯磨き粉を選んでも、ブラッシングの方法が適切でなければ効果は十分に発揮されません。歯周病を予防するための基本的な磨き方をお伝えします。
歯と歯茎の境目を意識する
歯周病菌は歯と歯茎の境目に溜まりやすいです。歯ブラシの毛先を歯と歯茎の境目に45度の角度で当て、小刻みに動かして汚れをかき出す「バス法」という磨き方が効果的です。力を入れすぎると歯茎を傷つけてしまうため、軽い力で優しく磨くのがポイントです。
デンタルフロスや歯間ブラシの併用
歯ブラシだけでは歯と歯の間の汚れを完全に落とすことはできません。デンタルフロスや歯間ブラシを使って、歯間部の歯垢を取り除きましょう。歯周病が進行して歯間が広がっている患者さんには、歯間ブラシの使用をおすすめします。
正しいブラッシング時間と頻度
歯磨きは1日2回以上が理想です。1回あたり3分程度はかけて、磨き残しがないようにしましょう。特に寝る前の歯磨きは重要です。就寝中は唾液の分泌が減り、細菌が繁殖しやすくなるため、丁寧なケアが必要です。
まとめ

歯周病の予防には、適切な成分を含む歯磨き粉選びと、正しいブラッシング習慣の両方が欠かせません。どの歯磨き粉を使えば良いか迷う場合は、ぜひ一度当院にご相談ください。患者さん一人ひとりの噛み合わせや歯茎の状態に合わせたアドバイスをさせていただきます。毎日のケアでお口の健康を守り、将来の歯のトラブルを防ぎましょう。